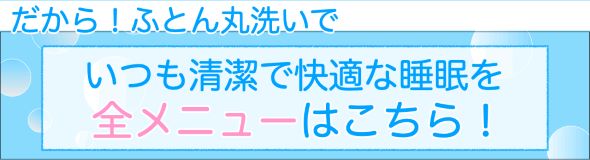全国一律 往復送料無料!北海道・沖縄・離島も含みます
- ホーム
- フレスココンテンツ
- 他社との違い 徹底解剖!
- ふとん丸洗いのパイオニア フレスコ
他社との違い 徹底解剖!
ふとん丸洗いのパイオニア フレスコ
非常識への挑戦
打ち直しから丸洗いへ
明治7年(1874年) フレスコのルーツとなるふとん店が誕生しました。
それから約150年、時代とともに寝具や寝具のメンテナンスに求められる条件も様々に変化をしてきました。

昔は、宿泊施設など貸しているふとんは、汚れたら打ち直し(※1)ができる綿ふとんが主流でした。
ところが、1982年に東京で発生したホテル火災が端緒となり、宿泊施設等には認証を受けた防炎寝具の使用が義務づけられるようになりました。
防炎寝具として認証を受けたふとんは、打ち直しをしてはいけないため、寝具のメンテナンスとして「洗うこと」が必然となりました。

昔は、宿泊施設など貸しているふとんは、汚れたら打ち直し(※1)ができる綿ふとんが主流でした。
ところが、1982年に東京で発生したホテル火災が端緒となり、宿泊施設等には認証を受けた防炎寝具の使用が義務づけられるようになりました。防炎寝具として認証を受けたふとんは、打ち直しをしてはいけないため、寝具のメンテナンスとして「洗うこと」が必然となりました。
まずは防炎寝具が完成しました。フレスコはホテル火災以前より、ふとん丸洗いにとりくんでいましたので、オリジナル仕様の洗濯脱水機、ふとんを動かさずに乾燥できる乾燥機、中わたまで洗えて傷めない洗剤の開発に次々と成功しました。ふとん丸洗いのトータルシステム『フレスコウォッシングシステム』を完成させ、ふとん丸洗いの先駆者となりました。このシステムをトータルで導入している工場は、2023年5月現在で20工場を超え、洗濯脱水機や洗剤についてはその何倍もの施設に導入いただいております。
- ※1汚れた中わたを取り出して洗ったあと、新しい側生地でくるむこと
ふとん丸洗い宅配サービスの誕生
フレスコウォッシングシステムの開発に成功したフレスコは「ふとんは洗わねばならい」を信念に各地でふとん丸洗いセミナーを開き、このふとん丸洗いシステムの普及に努めると同時に、ホームページを開設し各種の情報発信を行ってきました。
今でこそホームページがあるのは当たり前ですが、1996年当時は、ホームページを開設するだけで業界紙に載るくらいでした。2年後の1998年には、インターネットによる「ふとん丸洗い宅配サービスの注文受付を開始しました。

自宅でいつでも簡単に注文できて、ふとんも自宅で宅配便に預けるだけなので、ふとんを店頭へ持ち込む必要もなく、手軽に利用できます。この便利さが注目され、多くの業者が宅配サービスを展開していますが、これもフレスコが最初に始めたものです。今では、インターネットの検索結果が160万件を超えるまで拡がっています。ふとん丸洗いの普及に、この宅配サービスの販売が大きな役目を果たしました。
「洗ったつもり」でなく 「きちんと洗う本物」の丸洗いを選んでください
すべての丸洗い業者が、ふとんの中わたまでしっかり洗えているわけではありません。疑似的な汚れをつけた布をふとんの中に入れて、他社の丸洗いに出してみますと、残念ながらほとんど布の汚れが落ちていない業者もありました。普段、私たちは、ふとんの「中わた」を見ることはできません。側生地を漂白するだけの洗い方でもシミが取れていれば、ふとんがキレイになったと感じるのも事実です。
しかし、汗をはじめ様々な汚れは、側生地を通り抜け、ふとんの中わたに蓄積していまきす。この汚れを取り除くことが本当のキレイ。汗などは水溶性の汚れですから、フレスコウォッシングシステムなら清潔にできます。せっかく費用をかけて丸洗いをするのですから、キレイにしたつもりの丸洗いより、本当に清潔にする丸洗いを選んでいただきたい。ホームページでは、工程の詳しい解説や動画も公開しています。
フレスコでは、これからもふとん洗いの正しい情報を発信し続けます。ふとん丸洗いならフレスコと言われるように開発と改良も重ねてまいります。本当の『ふとん丸洗い』が認知され、どこでも安心して頼めるサービスとして信頼される産業に育っていくこともフレスコの願いです。

フレスコの
ふとん丸洗いクリーニングは
専用の“配送袋”
に入れて送るだけ!
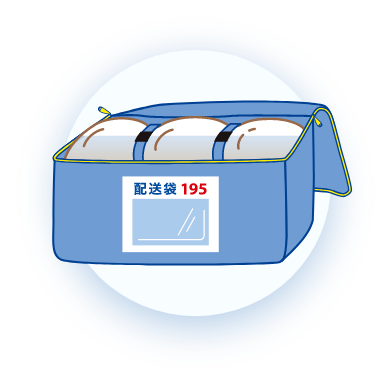
会員登録して購入ポイントも
レビュー投稿ポイントもゲット!
当社のサービス・製品につきまして、わからない事、疑問に思う事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。お電話、またはメールフォームにて承っております。お問い合わせの前に下記のページもご覧ください。
お電話でのお問い合わせは
通話料無料のこちらから
携帯電話・IP電話(有料)からは
[受付時間] 9:30~16:30
※土日祝・年末年始休み
お店で注文!
お店へ持ち込み!
フレスコのふとん丸洗いは
ネット注文以外
も受付中です!
- 企業・施設の方へ
- 法人向けふとん丸洗いの
お問い合わせ・お見積り
はこちら
ご利用ガイド
送料について
全国一律送料無料!
送料は北海道、沖縄、離島含む日本国内全国一律無料になります。
営業日カレンダー
- ・定休日は発送キットの出荷はできませんのでご了承ください。
- ・ご注文は24時間受け付けております。
- ・営業時間外は、受注に関する処理・メールの返信・お問い合わせに関する返信(電話含む)をお休みさせて頂いております。
お客様相談室 業務時間
◆業務時間
平日:9:30~16:30
◆定休日
土曜日・日曜・祝日
※年末年始等の定休日は定休日カレンダーをご参照ください。
お支払い方法

クレジットカード決済、Amazon Pay、楽天ペイ、コンビニ決済(前払い)、代金引換、PayPay、ペイディがご利用になれます。
キャンセルについて
◆キットに不備があった場合
商品には万全を期しておりますが、万一、商品に不備や破損があった場合、またはご注文の商品と異なる場合は、キット到着後8日以内にお客様相談室0120-310-730(携帯・IP電話
06-4964-1248(有料))までお電話、またはメールにてご連絡後、当社が指定する住所に速やかにご返送ください。送料は当社負担で、良品と交換させていただきます。
◆お客様の都合による場合
キット到着後8日以内にお客様相談室0120-310-730(携帯・IP電話
06-4964-1248(有料))までお電話、またはメールにてご連絡後、送料お客様負担で配送キットを当社が指定する住所まで返送ください。当社にキット到着確認後、配送料・振込手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。
◆ふとん発送後
キャンセルはお受けできません。ご了承くださいませ。